ホームセンターに行けば、ドドンッと目につくお米よりも大きな「○○石灰」の袋。

園芸や家庭菜園をされている方にとっては、売り切れだったら一番困る物の一つかもしれません。
『消石灰』『苦土石灰』『有機石灰』、今日のお買い得はこれなのねぇ~、 といって選ぶわけにもいかないこの3つ。
それぞれの
特徴や違いをまとめてみました!
ますます綺麗なお花やおいしいお野菜を育て、見たり食べたりする皆様を楽しませてあげてくださいね!
目次
「消石灰と苦土石灰と有機石灰」の違いを超簡単に説明
できれば弱酸性から中性の土で育ちたい植物。けれど雨などの影響もあり、酸性寄りになってしまうことが多い日本の土壌事情。
それを中和させるのに欠かせないのが、この石灰類です。
一番アルカリ成分の強い『消石灰』はカルシウムの補給と共に土壌の酸性度(PH)を中和してくれます。初めて作付けする畑や、酸性度が特に高い場合に使用すると効果的です。
『苦土(くど)石灰』は
『消石灰』にプラス、マグネシウムを含む石灰です。土壌を中性に近づけ、カルシウムはもちろん、さらにマグネシウムの補給にまで役立ってくれます。
『有機石灰』、こちらの特徴は
「穏やかな中和」です。
それにより、撒いてから1,2週間程度置いての種まきや植え付けが理想とされる『消石灰』『苦土石灰』のような無機石灰とは異なり、時間を置かずに作業を進めることができる、というのが一番の特徴となります。
消石灰とは?
生石灰を水と反応させ、不活性化させたものが『消石灰』です。
石灰=カルシウムを含み、PH12の強いアルカリ性を持つため、少量で、土壌の中和を促すことができます。
散布の目的は土壌の中和がメイン。プラスカルシウムの補給、です。
一度にたくさんの散布は、土を固めてしまい根が成長できなくなってしまうので、気を付けてくださいね。
またこの消石灰、アルカリ成分が強いため、急な中和となります。その間、土は大きく変化し続け、そのため土の状態が馴染む1週間ほどは放置しておく必要があるわけです。
消石灰には肥料成分は含まれていないため、手っ取り早く同時に肥料も撒きたいところですが、そこもまた我慢です。
散布後、土に馴染むのを待たず、同時に混ぜてしまうとアンモニアガスが発生します。このガスが植物の体内に入ると、酸素が奪われ、枯れてしまうのです。
つまり、種をまいたり、苗の植え付けをする2週間前に『消石灰』を、そのまま1週間置き、肥料を混ぜ、その1週間後にやっと種や苗の登場です。
……待つだけですが、根気がいりそうですね。
学校でライン引きに使われる、あの白い粉の正体も実はこの『消石灰』。
園芸売り場などで10キロ20キロを500円~1000円ほどで購入できる、大変リーズナブルな消石灰ですが、グラウンドで、日々の消耗品としてバシバシ使っていたことを思い出すと、なんとも納得させられるお値段でもありますね。
(PHとは0~14で表す酸性度のことです。PH7を中性とし、それより小さい数字ほど酸性度が高く、大きくなるほどアルカリ寄りとなります)
広告
苦土石灰とは?
◆『石灰の種類』の動画もどうぞ♪





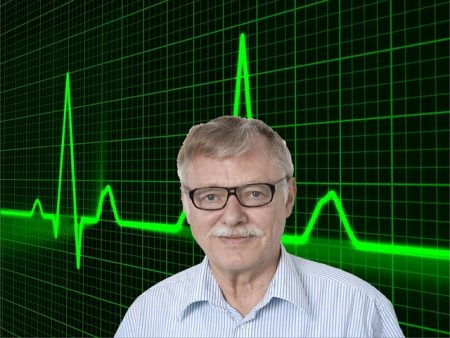



コメント